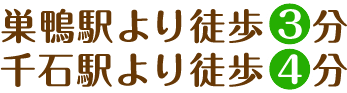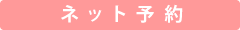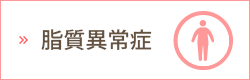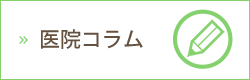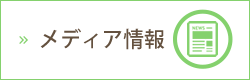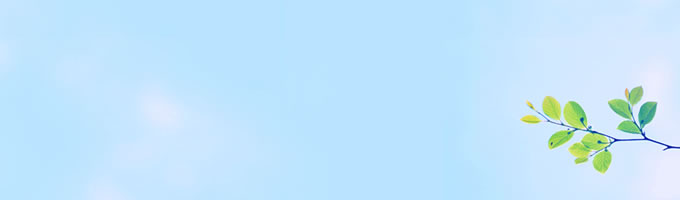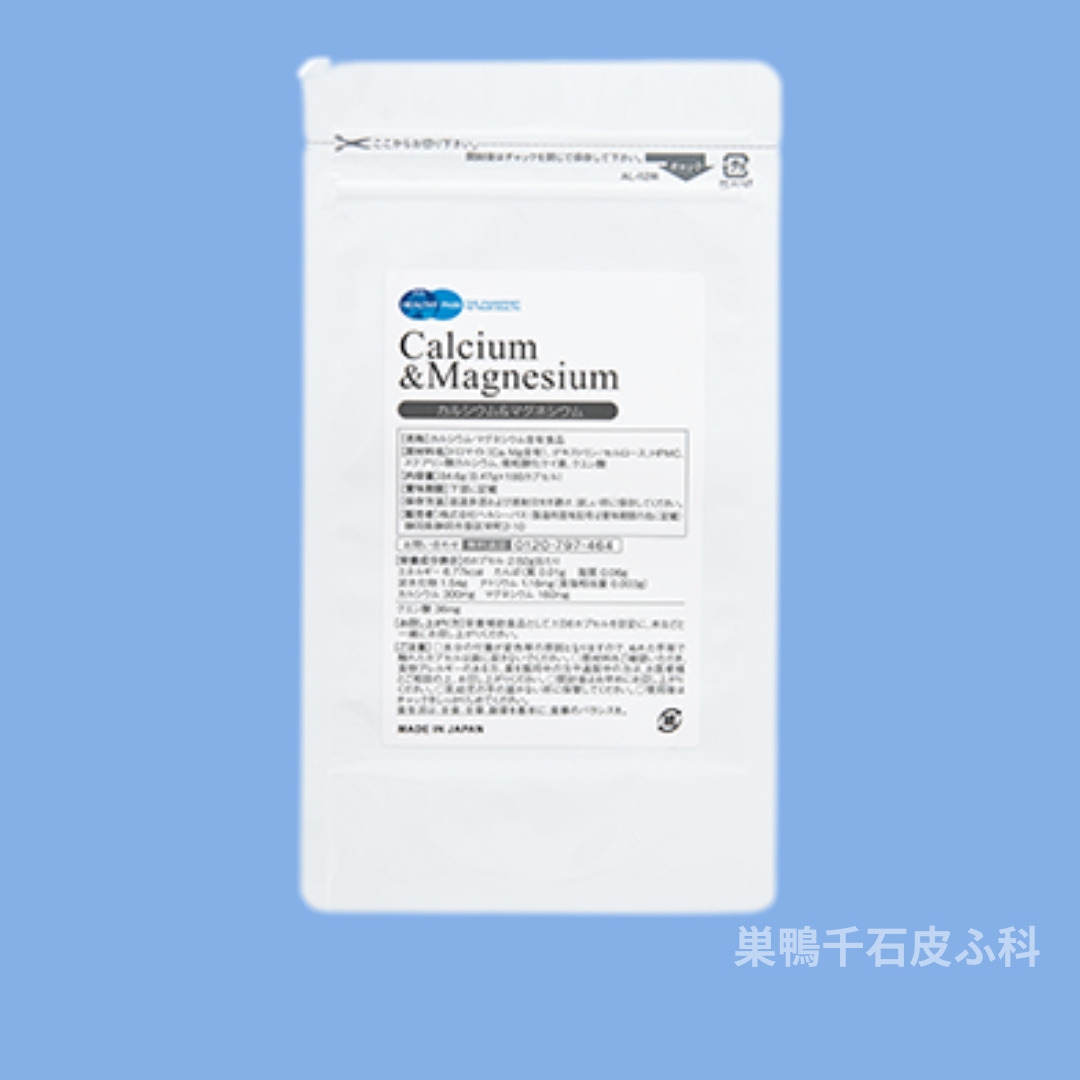健康の土台作りに―注目したいミネラルバランス
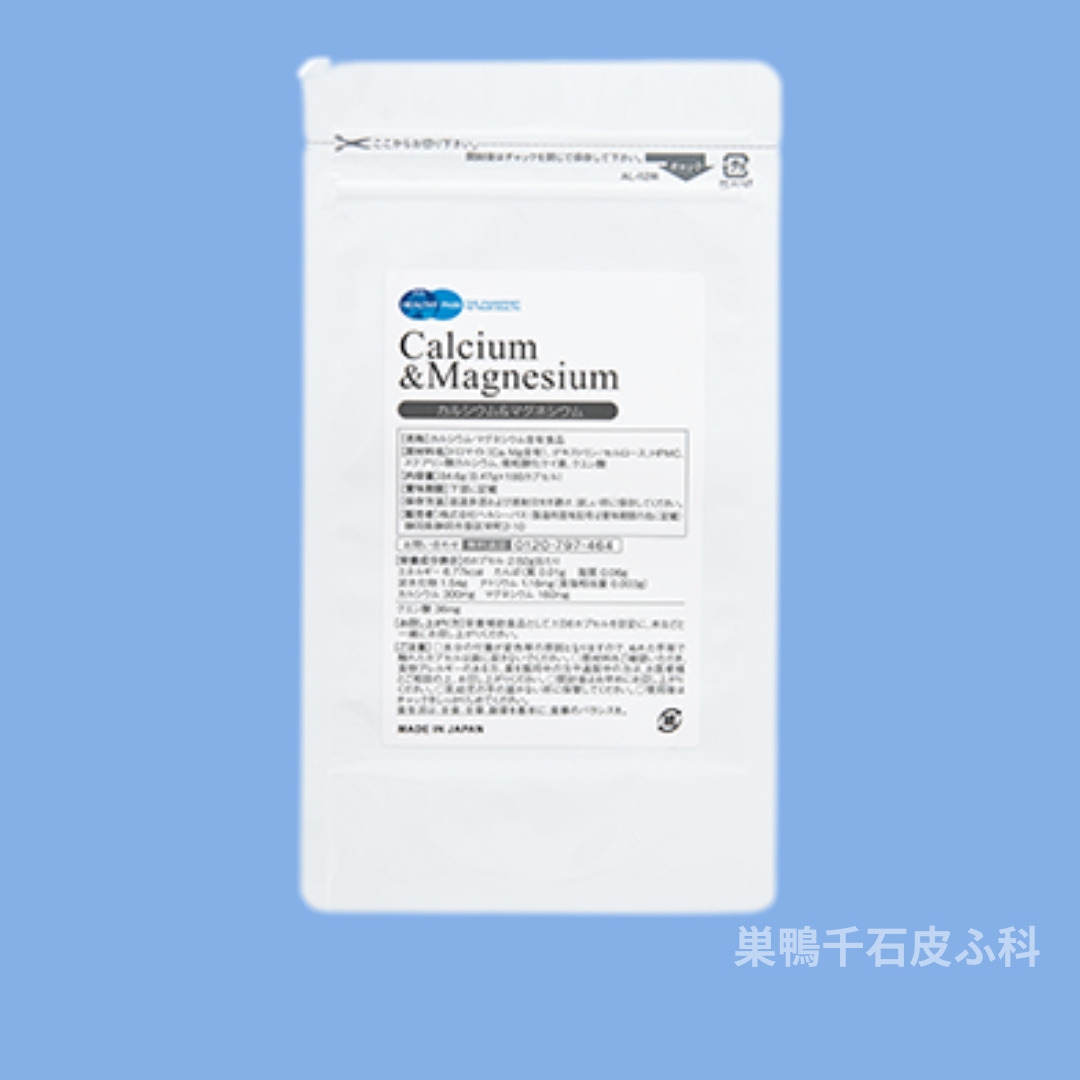
「健康診断で骨がもろくなっているといわれた」
「体にうまく力が入らないことがある」
「イライラを感じやすい」
といったお悩みはありませんか?
このような目に見えにくい不調には、カルシウムやマグネシウムといったミネラル不足が影響していることがあります。
健康維持に必要なミネラルは10種類以上ありますが、これらは体内で作ることができないため、食事などから補わなくてはなりません。
しかも、ミネラル類はバランスよく摂取しないとその働きが十分に発揮されず、ほかのミネラルの吸収を妨げてしまうこともあります。
このようなことから、体に不足しがちなミネラルをバランスよく補う手段として、サプリメントが選ばれるようになっています。
カルシウムとマグネシウムが支える身体の健康
カルシウムは、骨や歯を構成するミネラルとして知られています。
そのほかにも、筋肉の収縮や神経の伝達、血液が固まるのをサポートする働きやストレスをやわらげる作用など、心身の健康を支える重要な役割を担っています。
マグネシウムもまた、骨や歯の発育・強化に欠かせないミネラルです。
体内で行われる多くの酵素反応やエネルギー産生に関わるなど、カルシウムと同じように健康維持に欠かせないミネラルといえます。
カルシウムとマグネシウムは体内で互いに影響しあうことが知られており、特にカルシウムが筋肉を収縮させる作用を持つのに対してマグネシウムはその収縮を緩める役割を担っていることから、両者がバランスよく存在すると筋肉や神経の働きが安定しやすくなります。
また、カルシウムが骨の主成分として骨の強度に影響する一方で、マグネシウムは骨の柔軟性や弾力性に寄与します。マグネシウムが不足すると骨の質が低下することもあるため、両者のバランスがとても大切です。
意外に足りていない日本人のミネラル摂取状況
カルシウムやマグネシウムは体内で作ることができないため、毎日の食事などから積極的に摂取しなければなりません。
カルシウムの食事摂取基準(推奨量)は成人男性で750~800mg/日、成人女性で600~650mg/日、マグネシウムの食事摂取基準(推奨量)は成人男性で330~380mg/日、成人女性で270~290mg/日ですが、いずれの摂取量も全世代の男女で足りていないのが現状です。
表1:カルシウムの食事摂取基準(推奨量)(mg/日)と実際の摂取量(1日当たり平均値:mg/日)
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書および令和5年「国民健康・栄養調査」より作成
表2:マグネシウムの食事摂取基準(推奨量)(mg/日)と実際の摂取量(1日当たり平均値:mg/日)
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書および令和5年「国民健康・栄養調査」より作成
食事の内容に気をつければ、カルシウムやマグネシウムの不足を補うことは可能かもしれません。
ただ、毎日これらのミネラルをほかの栄養成分にも配慮しながら十分に摂るのはなかなか難しいものです。
そのようなときに役立つのが、カルシウムとマグネシウムをバランスよく摂取できるサプリメントです。
「カルシウム&マグネシウム」の特徴
「カルシウム&マグネシウム」とは
「カルシウム&マグネシウム」は、カルシウムとマグネシウムを同時に摂取できるサプリメントです。
カルシウムとマグネシウムは1:1~2:1の比率で摂取するのが理想的とされていますが、「カルシウム&マグネシウム」はカルシウム300mgに対してマグネシウムを160mg配合。
カルシウムとマグネシウムの吸収を助けるクエン酸も配合されているため、効率よく栄養成分を摂取できます。
なお、原材料である「ドロマイト」とは、サンゴなどの海の生物が長い年月をかけて海底に堆積し、石灰石となったものが海水中のマグネシウムなどと反応してできた生物由来の鉱物です。
ドロマイト原料のなかには有害な重金属が混入しているものもありますが、「カルシウム&マグネシウム」は重金属を含まない高品質なドロマイトのみを使用しています。
「カルシウム&マグネシウム」の成分など
- 6カプセルあたりエネルギー:6.77kcal、たんぱく質:0.01g、脂質:0.06g、炭水化物:1.54g、ナトリウム:1.16mg(食塩相当量0.003g)
- アレルギー表示(特定原材料等28品目)なし
- 配合栄養素(6カプセルあたり)栄養成分:カルシウム 300mg、マグネシウム 160mg、クエン酸 360mg
「カルシウム&マグネシウム」の摂取方法
「カルシウム&マグネシウム」は、1日6カプセルを目安に、水などで摂取してください。
ただし、普段の食事の内容などにより適切な摂取量は変わってきます。
摂取にあたっては、医師の指示に従ってください。
摂取タイミングは特に決まっていません。
飲み忘れがないように、毎日の摂取時間をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
「カルシウム&マグネシウム」はこんな方におすすめ
「カルシウム&マグネシウム」は、カルシウムとマグネシウムを理想のバランスで配合した医療機関専用サプリメントです。
そのため、以下のような方におすすめです。
- 忙しくて食生活が乱れがちな方
- 骨の健康が気になる方
- イライラなどメンタル面の不調が気になる方
- 健康維持を習慣化したい方
- 市販の健康食品に不安がある方
「カルシウム&マグネシウム」を摂取するうえでの注意点
摂取にともない生じる可能性のある体調変化
カルシウムやマグネシウムの摂取量が多くなりすぎると、お腹がゆるくなることがあります。
摂取にともない、軟便・下痢などが続いたり悪化したりする場合は主治医にご相談ください。
他の治療薬やサプリメントとの併用について
医療機関で薬を処方されている場合は、「カルシウム&マグネシウム」を摂取する前に併用の可否を主治医にご相談ください。
医療用医薬品のなかには、「カルシウム&マグネシウム」に含まれる栄養成分を主成分とするものもあるため、気づかないまま併用すると過剰摂取になるおそれがあります。
また、薬剤のなかにはカルシウムの吸収を促進するもの(ビタミンD製剤など)もあるため、注意が必要です。
他のサプリメントとの併用を希望する場合も、あらかじめ主治医にご相談ください。
栄養成分の過剰摂取や不必要な成分の摂取は、かえって体調不良をまねくおそれがあります。
特定の患者さまへの使用に関して
妊娠中または授乳中の方への使用に関して
「カルシウム&マグネシウム」に含まれる栄養成分は通常の食品にも含まれているものですが、妊娠などをしていない一般の成人を対象とした設計になっています。
また、本品に限らず、サプリメントは摂取することで病気が治ったり、より健康が増進したりするものではありません。
妊娠中や授乳中は栄養バランスに一層の配慮が必要なため、摂取にあたってはあらかじめ産婦人科医に相談することをおすすめします。
お子さまへの使用に関して
乳幼児・小児と成人では、必要なカルシウム・マグネシウムの量が異なります。
またお子さんの場合、食事量や成長の程度も個々でかなり違うと考えられます。
その他、幼いお子さんについてはカプセルを誤嚥するリスクもあるため、注意が必要です。
このようなことから、乳幼児・小児については摂取をおすすめしません。
「カルシウム&マグネシウム」の費用
「カルシウム&マグネシウム」は、1瓶180カプセル入り(1日6カプセル摂取で約1ヵ月分)で3300円です。
医療用医薬品ではなく、保険の適用もないため、全額自費負担になります。
なお、「カルシウム&マグネシウム」は医療機関専用のサプリメントなので、ドラッグストアなどでは購入できません。
よくあるご質問
- 「カルシウム&マグネシウム」の原材料であるドロマイトは海で取れるそうですが、ヨウ素は含まれますか?
-
メーカーによると「カルシウム&マグネシウム」を過去に分析した際には、ヨウ素は検出されていないとのことです。
- 骨を強くするために、「カルシウム&マグネシウム」とあわせて牛乳もたくさん飲んだほうが良いですか?
-
大量の牛乳を摂取すると、高カルシウム血症になったり体内がアルカリ性に傾いたりする症状をまねくおそれがあります。今までの食生活を変える場合は、あらかじめ主治医と相談し、必要に応じて摂取量の変更などの指示を受けてください。
- 「カルシウム&マグネシウム」を飲み忘れた場合は、どうすればいいですか?
-
「カルシウム&マグネシウム」を飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を服用すれば大丈夫です。なお、何日も飲み忘れた場合でも、1日の目安量を超えて摂取するのは避けてください。過剰摂取は、体調不良をまねくおそれがあります。
記事制作者
木村眞樹子
東京女子医科大学卒業。循環器内科専門医、内科、睡眠科において臨床経験を積む。
東洋医学を取り入れた漢方治療にも対応。
オンライン診療に積極的に取り組む3児の母。