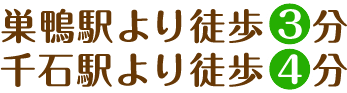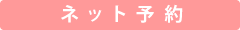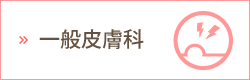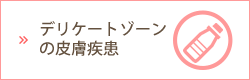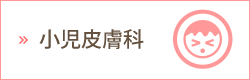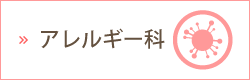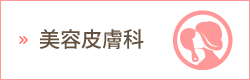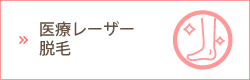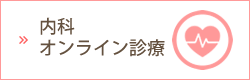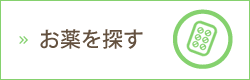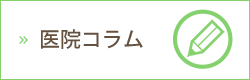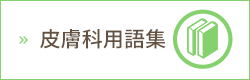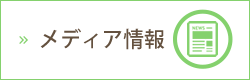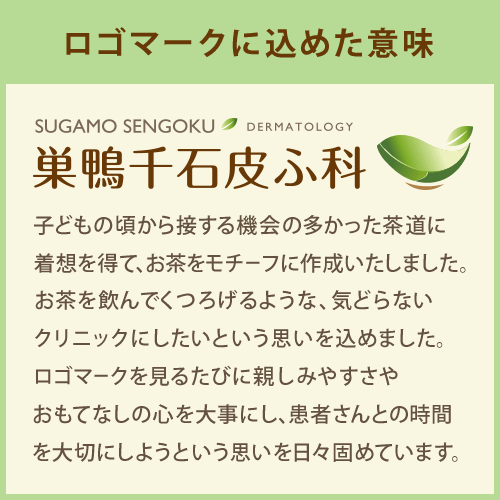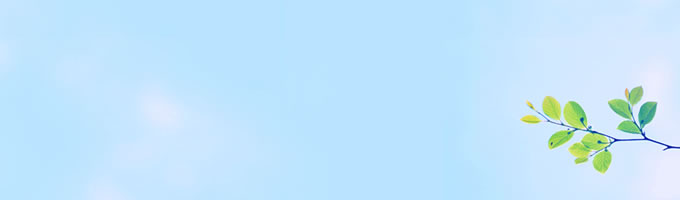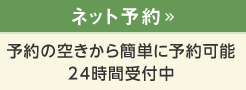竹筎温胆湯とは

咳や痰が多く、安眠できないような場合に用いられる漢方薬です。インフルエンザやかぜ、肺炎の回復期に熱が長引いてしまったり、平熱になっても気分がさっぱりしないような方に用いられます。
出典は中国・明の時代に著された医学書である万病回春(まんびょうかいしゅん)です。
解熱作用のある竹筎を主薬とし、胆寒(驚きやすいなどの精神不安がある)の状態を温めて改善する薬効があることから処方名としています。
オンライン診療対応可能
当院では、初診からオンライン診療にて漢方薬の処方を行っております。通院なしで薬剤をお送りすることが可能です(送料無料)。アプリのインストールは不要で、システム利用料も徴収しておりません。よろしければご利用ください。
» オンライン診療の詳細はこちら
竹筎温胆湯の特徴
竹筎温胆湯は以下の生薬が含まれます。
- 半夏(ハンゲ)
- 柴胡(サイコ)
- 麦門冬(バクモンドウ)
- 茯苓(ブクリョウ)
- 桔梗(キキョウ)
- 枳実(キジツ)
- 香附子(コウブシ)
- 陳皮(チンピ)
- 黄連(オウレン)
- 甘草(カンゾウ)
- 生姜(ショウキョウ)
- 人参(ニンジン)
- 竹筎(チクジョ)
竹筎温胆湯の対象患者さまについて
効能効果はインフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきや痰が多くて安眠が出来ないものです。
使用目標は以下の通りです。
(使用目標=証)
比較的体力の低下した人で、感冒などで発熱が長びき、あるいは解熱後、咳が出て痰が多く、不眠を訴える場合に用いる。
1)精神不安、心悸亢進などを伴う場合。
2)季肋下部に軽度の抵抗・圧痛を認める場合(胸脇苦満)。
竹筎温胆湯の使い方
成人の場合、1日合計7.5gを2~3回に分割して食前もしくは食間に、水またはぬるま湯と一緒に内服します。なお用量は年齢・体重・症状により適宜増減します。また万が一飲み忘れてしまった場合は気がついた時点で内服して下さい。ただし次に飲む時間が近い場合は1回飛ばして次の分から再開しましょう。
竹筎温胆湯を服用する上での注意点
重大な副作用として偽アルドステロン症、ミオパチーが報告されています。その他、過敏症(発疹、蕁麻疹等)が報告されています。服用していつもと体調が違うようでしたら服用を中止し、医師へ相談してください。使用経験が少ないため、小児に対する安全性は確立していないと添付文書では記載されています。用量については医師の指示に従ってください。
竹筎温胆湯の患者さま負担・薬価について
医療用とされている竹筎温胆湯としては「ツムラ竹筎温胆湯エキス顆粒(医療用)」が有名です。1日薬価は215.25円で1包(2.5g)あたり71.75円です。1日3包で30日分処方された場合、3割負担の患者さまでは1937.25円の薬剤費となります。(薬剤費のみの計算です)
よくあるご質問
- 竹筎温胆湯にはどんな副作用がありますか?
-
詳しくはこちらを参照ください。
症状に気づいた場合は、使用をやめ、処方元の医師や薬剤師にご相談ください。
- 竹筎温胆湯はどんな効果がありますか?
-
せきや痰が多く、安眠できないような方に効果が期待できる漢方薬です。
- 竹筎温胆湯はドラッグストアで売っていますか?
-
第二類医薬品として販売されています。詳しくは各販売店舗にお問い合わせください。
- ほかにどんな漢方薬がありますか?
-
漢方薬には多くの種類があり、国内で医療用として承認されたものは148処方あります。詳細はこちらのページをご覧ください。
» 漢方薬の詳細はこちら
記事制作者
小西真絢(巣鴨千石皮ふ科)
「巣鴨千石皮ふ科」院長。日本皮膚科学会認定専門医。2017年、生まれ育った千石にて 「巣鴨千石皮ふ科」 を開院。
2児の母でもあり、「お肌のトラブルは何でも相談できるホームドクター」を目指しています。