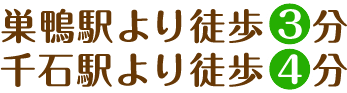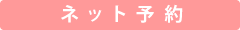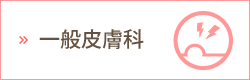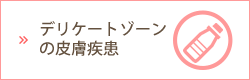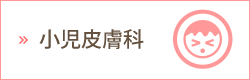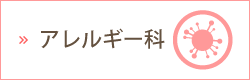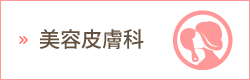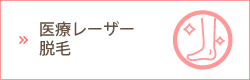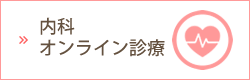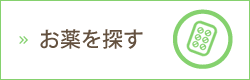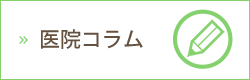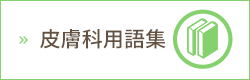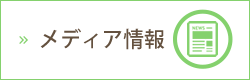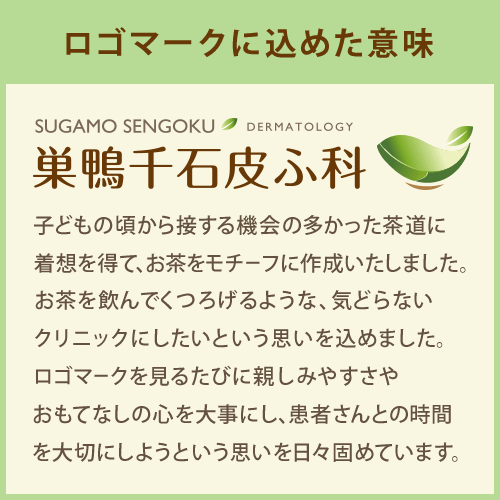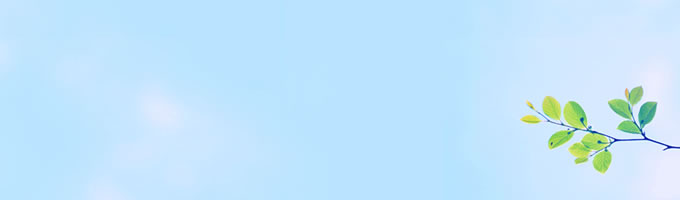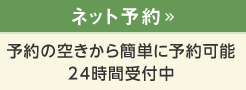最終更新日:2026年02月18日

目次
高血圧と食事の関係
食生活と関係が深い日本人の高血圧
『高血圧治療ガイドライン2019』によると、高血圧と診断されるのは、診察室で測定した収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)90mmHg以上の場合です。
日本人の高血圧は、血圧が高くなる原因が特定できない本態性高血圧が約9割だといわれています。本態性高血圧は、塩分の過剰摂取や肥満、飲酒、運動不足、ストレス、遺伝的な体質などさまざまな要因が関与していると考えられていますが、特に日本人の高血圧は、塩分の過剰摂取との関係が深いとされています。
また、最近は若い世代の男性を中心に肥満(特に内臓脂肪が増えるタイプの肥満)をともなう高血圧が増えてきています。内臓脂肪の増加も食習慣と関係が深いため、過栄養をまねきやすい食生活(食べ過ぎや飲み過ぎ、早食いなど)に心当たりがある場合は注意が必要です。
塩分の過剰摂取や過栄養が血圧に良くない理由
塩分の過剰摂取が血圧におよぼす影響
塩分(ナトリウム)を摂り過ぎると、体内の塩分濃度が高くなります。すると、塩分濃度を低くするために体液量が増え、血液量も増加します。血液量が増えると血管にかかる圧力が高くなるため、血圧が上昇すると考えられています。
また、体内の塩分濃度が高い状態が続くと、塩分や水分などをろ過・再吸収する腎臓にも大きな負担がかかります。腎臓のろ過機能が低下して塩分や水分の排出が滞ると、血液量のコントロールがうまくいかなくなります。そのため、血圧のさらなる上昇をまねく結果となります。
過栄養による内臓脂肪の蓄積が血圧におよぼす影響
栄養を摂り過ぎて内臓脂肪が過剰になると、脂肪細胞から分泌される生理活性物質のバランスが乱れて血圧の上昇をまねきやすくなります。
また、内臓脂肪が増えるとインスリン(糖をエネルギーに変えるホルモン)の働きが悪くなります。すると、膵臓から分泌されるインスリン量が増えますが、インスリンには腎臓による塩分排出を妨げる作用があるため、結果として血液中の塩分濃度が高くなり、血圧が高くなります。
食事で血圧が下がることは臨床研究でも証明済み
食事内容の改善で血圧が下がることは、多数の臨床研究ですでに証明されています。
特に塩分については、高血圧ガイドラインの上でも1日の摂取量を6g未満にすることで高血圧の予防、有効な降圧効果が得られることが明記されていますが証明されています。たとえ1日の塩分摂取量を6g未満にできなくても、1日に摂取する塩分量を2.5g減らすだけで降圧効果が得られるとされています。
そのほか、野菜や果物、低脂肪乳製品が豊富で、飽和脂肪酸(肉類に多く含まれる成分)とコレステロールが少ない食事に減塩食を組み合わせた食事で、降圧効果がもたらされることも報告されています。
また、オリーブオイルや多価不飽和脂肪酸(植物や魚の油に多く含まれる成分)が豊富な食事、魚介類や穀物、野菜、果物、豆類などが豊富で肉類が少ない食事で、より有効な降圧効果が得られることが報告されています。
血圧を下げる効果が期待できる食べ物・飲み物
生活を改善して血圧を下げるためには、塩分の摂取量を控えることが大切です。
しかし、塩分は醤油やみそなどの調味料、加工食品などにも多く含まれているため、摂取量を減らすのは容易なことではありません。
そこで、減塩と併せて行いたいのが、塩分の排出をうながす食品・塩分の吸収を抑える食品などの摂取です。
以下では、血圧を下げる効果が期待できる食品をその理由とともに紹介します。
カリウムを含む食べ物
カリウムには、塩分(ナトリウム)の排出をうながす作用があります。
カリウムを多く含むのは、野菜や豆類、果物などです。海藻類にも多く含まれていますが、ナトリウムの量も多いためおすすめできません。
| 食品名 | カリウムの量 (mg/100g) |
|---|---|
| ほうれん草 | 690 |
| 干し柿 | 670 |
| 里芋 | 640 |
| 人参 | 630 |
| 枝豆 | 590 |
| アボカド | 590 |
| さつまいも | 480 |
| じゃがいも | 420 |
| バナナ | 360 |
| メロン | 350 |
| キウイフルーツ | 300 |
効率よく摂取する方法および注意点
カリウムは水によく溶けるため、長時間ゆでたり水にさらしたりすると摂取できる量が減ってしまいます。加熱する際には電子レンジを利用し、水にさらす時間を短くするなどして、カリウムの流出を防ぐようにしましょう。
なお、腎臓に障害があり、医師からカリウムの摂取量を制限するよう指示されている場合は、野菜や果物などの積極的な摂取はすすめられません。
また、肥満や糖尿病などがあってエネルギー制限が必要な場合は、果物の1日摂取量を80kcal程度にとどめてください。
食物繊維を含む食べ物
食物繊維には、塩分(ナトリウム)の吸収を抑える作用があるとされています。また、糖質や脂質の吸収を抑える作用や満腹感を得やすくする作用もあるため、肥満の抑制にも効果が期待できます。
食物繊維は、肉や魚などの動物性食品にはほとんど含まれていませんが、植物性食品に多く含まれています。
| 食品名 | 食物繊維の量 (g/100g) |
|---|---|
| 干し柿 | 14.0 |
| じゃがいも | 9.8 |
| そば | 6.0 |
| ごぼう | 5.7 |
| アボカド | 5.6 |
| 生しいたけ | 5.5 |
| スパゲッティ(乾燥) | 5.4 |
| ブロッコリー | 5.1 |
| 枝豆 | 5.0 |
| 全粒粉パン | 4.5 |
| 食パン | 4.2 |
| えのき茸 | 3.9 |
| まいたけ | 3.5 |
| 玄米 | 3.0 |
| こんにゃく | 3.0 |
| さつまいも | 2.8 |
| キウイフルーツ | 2.6 |
| りんご | 2.5 |
効率よく摂取する方法および注意点
食物繊維の摂取量を増やしたいなら、1日のうち1食の主食を食物繊維の多い食品(玄米、全粒粉パンなど)に置き換えるのがおすすめです。
副菜として、食物繊維を多く含む食品を1品添えるのもよいでしょう。
麺類も比較的食物繊維が豊富ですが、めんつゆやパスタソースなどには塩分が多く含まれています。そのため、つゆを残したり減塩タイプのソースを選んだりするなどの工夫が必要です。
EPA・DHAを含む食べ物
魚油に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)には、血圧を下げる作用があることが知られています。EPA・DHAは特に青魚に多く含まれています。
| 食品名 | EPAの量 (mg/100g) |
DHAの量 (mg/100g) |
|---|---|---|
| さんま | 850 | 1600 |
| さば | 690 | 970 |
| さけ | 492 | 820 |
| あじ | 300 | 570 |
| あなご | 560 | 550 |
| くろまぐろ | 27 | 120 |
効率よく摂取する方法および注意点
魚の調理が面倒な場合は、缶詰を利用すると便利です。塩分の摂り過ぎにならないように、水煮タイプのものを選ぶのがおすすめです。
なお、EPA・DHAはサプリメントとしてもよく販売されており、動脈硬化の予防としても有効ですが摂取量が多くなりすぎると出血が止まりにくくなったり(鼻血、内出血など)、おなかがゆるくなったりすることもあるため注意が必要です。
血圧を下げる効果が期待できる飲み物
血圧を下げる効果が期待できる飲み物としては、食塩無添加の野菜ジュースや果物ジュース、緑茶、飲用の酢などがあります。
これらの共通点は、「塩分がほとんど含まれていないこと」「血圧降下作用が期待できる成分が含まれていること」です。
| 飲み物の種類 | 血圧降下作用が期待できる理由 |
|---|---|
| 食塩無添加の 野菜ジュース 果物ジュース |
ナトリウムの排出をうながすカリウムや 食物繊維を多く含むため。 |
| コーヒー | ナトリウムの排出をうながす カリウムの量が比較的多いため。 血管の老化予防に役立つとされる ポリフェノールを豊富に含むため。 |
| ココア | ナトリウムの排出をうながす カリウムや食物繊維を多く含むため。 血管の老化予防に役立つとされる ポリフェノールを豊富に含むため。 |
| 緑茶 | 血管の老化予防に役立つとされる ポリフェノールを豊富に含むため。 |
| 豆乳 | ナトリウムの排出をうながすカリウムや 食物繊維を多く含むため。 |
| 飲用の酢 (りんご酢など) |
主成分である酢に、血管拡張作用 などがあるため。 |
摂取する際の注意点
いずれの飲み物を摂る場合も、過栄養にならないように注意が必要です。
野菜ジュースや果物ジュースは、糖分が加えられてないものを選ぶようにしましょう。コーヒーやココアも無糖のものを選んでください。豆乳や酢は、甘味料が加えられてないものを摂取するようにしましょう。糖尿病を指摘されている方は主治医と相談するとよいかもしれません。
コーヒー・ココア・緑茶については、カフェインの量にも注意してください。カフェインを摂り過ぎると、不眠やめまい、吐き気や下痢を起こすことがあります。また、長期的にカフェインの過剰摂取が続くと、高血圧になるリスクが高くなる場合もあるとされています。
健康食品を薬のかわりに使うのはNG!
血圧を下げるために、健康食品の利用を考える方もいらっしゃることでしょう。
たしかに、特定保健用食品(トクホ)のなかには降圧作用が期待できる成分が配合されているものもあります。ですが、トクホの申請に必要な臨床試験は医療用の降圧薬の承認に必要な臨床試験に比べて期間が短く、被験者の人数が少ない場合もあります。そのため、降圧効果の確実性という点では、検証に不十分な部分があるといえます。
このようなことから、トクホなどの健康食品を医療用の降圧薬のかわりに使うことはおすすめしません。
参考:「高血圧治療ガイドライン2019」Q5特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品に降圧効果はあるのか?より
血圧を下げるためには食生活以外にも注意が必要
血圧を下げるためには、食生活の改善だけではなく適度な運動やストレス管理なども大切です。
『高血圧治療ガイドライン2019』では、食生活以外の生活習慣の修正ポイントとして以下の項目を挙げています。
- 適性体重の維持:BMI(体重[kg]/身長[m]2)25未満を維持。
- 運動:軽い有酸素運動(早歩きやジョギングなど)を1回30分以上、または1回10分以上トータルで40分以上運動を週に3回以上行う。
- 節酒:男性は20~30mL(日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、焼酎なら半合、ウィスキー・ブランデーならダブルで1杯、ワインならグラス2杯が目安)/日以下、女性は10~20mL/日以下に抑える。
- 喫煙習慣:禁煙する。受動喫煙も避ける。
- その他:寒冷によるストレス、急激な感情変化にともなうストレスを避ける。
食生活の改善も含め、このような生活習慣の改善を合わせて行うと、より効果的に血圧を下げることができます。
血圧を下げたい方のオンライン診療
食生活の改善も含め、生活習慣の改善(非薬物療法)は血圧を下げるのに有効ですが、薬による治療が始まってからも非薬物療法は続けなければいけません。実際、降圧薬だけでは十分な効果が得られない方でも、降圧薬+非薬物療法で目標とする血圧値に到達できることもあります。
しかし、食生活の改善などは継続が難しく、途中で挫折してしまう方も少なくありません。
そこでおすすめなのがオンライン診療です。オンライン診療なら通院しなくても医師のアドバイスが受けられるため、忙しい方でも継続して非薬物療法に取り組めるでしょう。
当院では、初診からオンライン診療で高血圧の薬物療法はもちろん、非薬物療法についてもオンライン診療で対応しております。血圧を下げるために生活習慣の改善に取り組みたい方・どのように食事を改善すればよいのかわからない方などのご利用をお待ちしております。
アプリのインストールは不要で、システム利用料も徴収しておりません。よろしければご利用ください。
- 下記のいずれかのボタンからお申込みください。
高血圧の処方薬一覧
詳細はこちら
| 分類 | 商品名 | 一般名 |
|---|---|---|
| カルシウム 拮抗薬 |
ノルバスク アムロジン |
アムロジピン |
| アテレック | シルニジピン | |
| アダラート | ニフェジピン | |
| カルブロック | アゼルニジピン | |
| ACE阻害薬 | レニベース | エナラプリル |
| ARB | ニューロタン | ロサルタン |
| ブロプレス | カンデサルタン | |
| ディオバン | バルサルタン | |
| オルメテック | オルメサルタン | |
| ミカルディス | テルミサルタン | |
| アジルバ | アジルサルタン | |
| ARNI | エンレスト | サクビトリル |
| MRA | セララ | エプレレノン |
| ミネブロ | スピロノラクトン | |
| α遮断薬 | カルデナリン | ドキサゾシン |
| β遮断薬 | インデラル | プロプラノロール |
| メインテート | ビソプロロール | |
| アーチスト | カルベジロール | |
| 利尿薬 | フルイトラン | トリクロロメチアジド |
| アルダクトン | スピロノラクトン | |
| ラシックス | フロセミド | |
| ナトリックス | インダパミド | |
| ダイアート | アゾセミド |